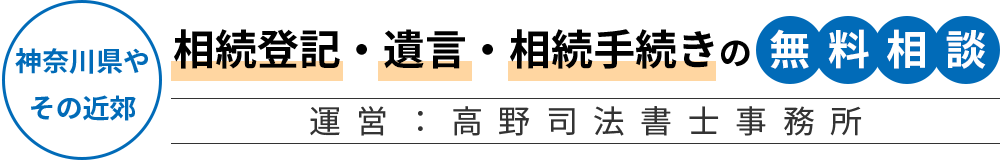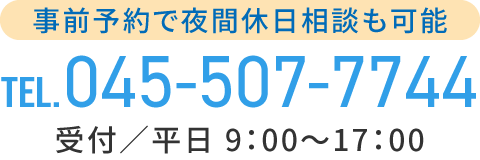遺言書で定められる内容(遺言事項といいます)も民法などの法律で規定されています。遺言事項以外を遺言書に記載できない訳ではありませんが、法的拘束力は生じません。
ここでは遺言書でどのようなことを定められるのか(遺言事項)についていくつか見ていきましょう。
このページの目次
1.相続に関する事項
相続分の指定
相続人の全部または一部の者について、民法で規定されている法定相続分とは異なる割合で相続分を定めることが出来ます。
例えば、相続人が配偶者と子供1人である場合、法定相続分は「配偶者が2分の1、子供が2分の1」ですが、「配偶者に財産の4分の3を、子供に4分の1を相続させる」というように指定することが可能です。
遺産分割方法の指定、遺産分割の禁止
遺産分割方法の指定とは、どの財産を相続人の中の誰に残すのかを遺言書で指定する方法です。
例えば「自宅の土地と建物は妻に、預貯金は長男に、株式は長女に相続させる」のように特定の財産を特定の相続人に処分する形で指定する方法が一般的です。
また、遺産分割を禁止する内容の遺言を作成することも可能です。この期間は遺言者が亡くなってから5年間に限られますが、例えば相続人の中に未成年者がいる場合や、相続人間で揉めておりすぐに話し合いを開始できそうにない場合に、少し期間を空けるためにこのような内容の遺言を残すことが出来ます。
特別受益持ち戻し免除
特別受益とは、一部の相続人のみが遺言者から受けた生前贈与や遺贈(遺言書で特定の者に財産を引き継がせること)のことを言います。
例えば、住宅購入資金や開業資金の贈与などがこれにあたります。一部の相続人のみに特別受益があると特別受益を受けていない相続人との間で不公平となってしまいます。そこで、特別受益の対象となる財産の額を含めて遺産分割の対象とすることで相続人間の公平を図る制度があり、これを特別受益の持ち戻しといいます。
遺言者は遺言書で、この特別受益持ち戻しを免除する意思表示をすることが出来ます。特別な取り分として生前贈与や遺贈を行った遺言者の意思を尊重する制度です。
推定相続人の廃除や取り消し
遺言書で遺言者に対して虐待や重大な侮辱を行った推定相続人(相続人となる予定の者)に対して、遺留分を含めた相続分のすべてを失わせる意思を表示することが出来ます。
この場合、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければなりません。ただし、廃除は必ず認められるというわけではありません。相続人にとって相続する権利は非常に重大な権利であるため、家庭裁判所での審査もかなり慎重に行われます。
また、事情が変わったり、遺言者自身の気持ちが変わることもあるため、遺言者は家庭裁判所に対し廃除の取り消しを請求することも出来ます。この手続を生前に行うことも、遺言書に残して相続後に行うことも可能です。遺言者の意思を尊重する制度であるため、廃除事由が消滅していない場合でも取り消しすることが可能です。
2.財産に関する事項
遺贈
遺言で、法定相続人やそれ以外の第三者(例えば、内縁関係にある夫や妻や身近で世話になった人など)に対し財産を譲り渡すことが出来ます。
これを遺贈といい、財産を譲り受ける人を受遺者といいます。
遺贈は個人に宛ててだけではなく、会社や学校法人、公益法人などの法人に遺贈(寄付)することも可能です。
3.身分に関する事項
認知
遺言によって認知をすることが出来ます。内縁関係など法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子供のことを非嫡出子といい、法律上の父親を確定するには認知の手続きが必要となります。
遺言で認知されると父親と法律上の親子関係が発生するため、父親の相続について相続する権利を持つことになります。遺言で非嫡出子を認知する場合は、遺言執行者が認知の手続きを行うため、遺言執行者の選任が必須となります。
未成年後見人の指定
遺言によって未成年の子供の未成年後見人を指定することが出来ます。未成年後見人とは親権者の死亡などにより未成年者に対し親権を行う者がいなくなってしまった場合に、未成年者の財産管理や契約等の法律行為を代理する者のことを言います。
未成年後見人が選任されると未成年者の戸籍に未成年後見人が選任されたことが記載されます。
4.遺言執行に関する事項
遺言執行者の指定または指定の委託
遺言執行者とは、相続開始後に遺言書の内容を実現する手続きを行う人のことです。
遺言者は遺言書で遺言執行者自体を指定したり、遺言執行者を決めてもらう人を指定することが出来ます。
5.その他
- 祭祀承継者の指定
- 一般社団法人(財団法人)の設立
遺言書を残したほうが良いケース
遺言書を残すことの大きなメリットの一つは、相続手続きにおいて大きな障壁となる遺産分割協議の手続きを回避できることです。その観点からどのようなケースで遺言書を残した方が良いのかいくつか見ていきたいと思います。
1.財産が自宅不動産しかない
不動産は相続財産の中でも分割をするのが難しい財産です。自宅を遺産分割する場合その方法には、現物分割(相続人間で自宅を持分で共有する)、換価分割(自宅を売却して、相続人間で売買代金を分配する)、代償分割(相続人の1人が自宅を取得して、その代償として他の相続人に金銭を支払う)の3つの方法があります。
現物分割で自宅を共有すると、自宅の管理について揉めたり、共有者全員の同意がないと自宅を売却出来ないなどのデメリットがあります。
代償分割の場合は自宅を取得した相続人に資金がない場合はそもそも選択出来ませんし、換価分割を選択した場合、配偶者あるいは同居している相続人は住む場所を失うことになりかねません。
2.夫婦間に子供がいない
夫婦間に子供がいない場合、残された配偶者は、義理の両親や義理の兄弟姉妹とともに相続人となり、財産の取得者を決めるには相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。
残された配偶者と義理の両親や義理の兄弟姉妹との仲が良くない、疎遠である場合は、遺産分割協議がまとまらない可能性があります。
3.離婚した相手との間に子供がいる
離婚した相手との間に子供がいる場合、離婚した相手は相続人ではありませんが、その子供は相続人となります。そのため、再婚している場合は現在の配偶者と離婚した相手との子供の間で遺産分割協議を行うこととなります。この場合も遺産分割協議がまとまらない可能性は高いでしょう。
4.内縁関係にある
婚姻届を提出せず夫婦同然の共同生活を営む男女関係を内縁関係と言いますが、法律上の夫婦とは認められず、内縁の妻(夫)は内縁の夫(妻)の法定相続人ではないので相続権はありません。内縁の妻(夫)に財産を残すのであれば遺言書は必須です。
5.財産を残したい人が決まっている
法定相続人であれば遺産分割協議によって遺産を取得できる可能性がありますが、法定相続人以外の人には遺言書がなければ財産を残すことが出来ません。法定相続人以外の人とは、例えば、内縁関係にある妻や夫、認知していない子供、友人や知人などです。
6.事業を営んでいる
個人事業であっても、会社経営であっても事業承継をスムーズに進めるためには遺言書が必要です。遺産分割協議で揉めて必要な財産(株式や事業資産など)を後継者が取得することが出来ないと事業承継に重大な影響を及ぼすことになりかねません。
7.相続人に判断能力の無い者や行方不明者がいる
相続人に判断能力が無い者いる場合は成年後見人の選任を、相続人に行方不明者がいる場合は不在者財産管理人の選任をそれぞれ家庭裁判所に申し立てなければなりません。
そこで選任された成年後見人や不在者財産管理人が判断能力が無い相続人や行方不明の相続人に代わって遺産分割協議に参加することになります。
成年後見人も不在者財産管理人も判断能力が無い相続人や行方不明の相続人の財産を守ることが仕事ですので、法定相続分を確保した遺産分割協議書でないと印鑑を押してくれません。